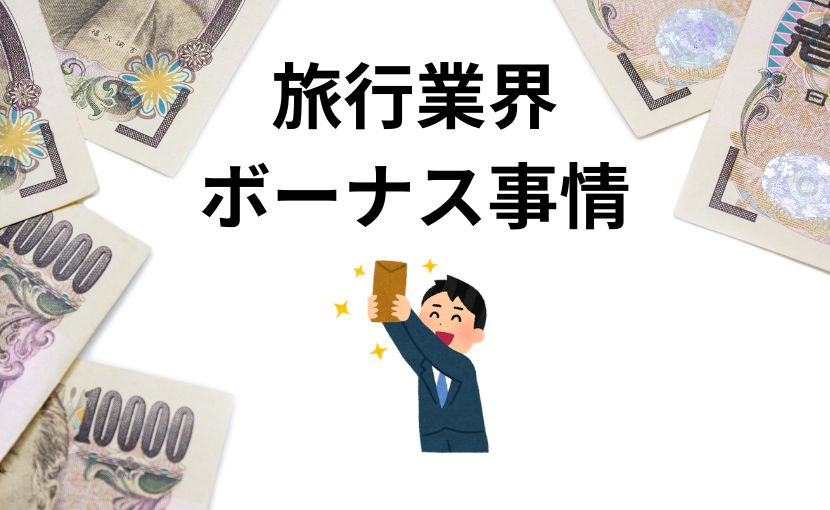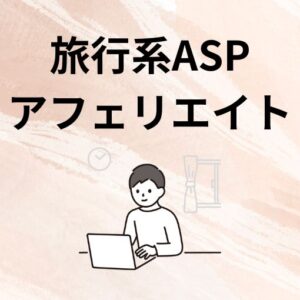【PR】本文中に広告リンクが含まれています。
2025年最新版の旅行業界におけるボーナス事情を詳しく解説します。
旅行業界は景気の影響を受けやすく、ボーナスの支給額や支給率に変動が生じやすい業界の一つです。
この記事では、ボーナスの基本や2025年夏の全産業動向、大手・中小企業の実態、旅行業界の特徴と他業種との比較を分かりやすく解説します。
最後に、ボーナスを増やすための具体的な方法もご紹介しますので、旅行業界で働く方はもちろん、これから業界を目指す方は是非参考にしてください。
コンテンツ
ボーナス(賞与)とは?意味と支給の仕組みを解説

金額の話に入る前に、そもそもボーナスとは何なのかを押さえておくことが重要です。
ここでは、ボーナスの仕組みや支給の実態について詳しく解説します。
企業の業績や評価に応じて変動する報酬であるボーナスの基本を理解したうえで、次章から具体的な支給額の動向について見ていきましょう。
業績に応じて配分される一時金
ボーナスは企業の業績や個人の評価に基づいて支給される一時金であり、業績が良ければ多く支給される一方、業績が悪い場合は減額されたり、支給が見送られたりすることもあります。
特に旅行業界のように景気や外部環境の影響を受けやすい業種では、ボーナスの変動が大きくなる傾向があります。
このため、毎月の給与とは異なり、安定した収入とは言えない側面があります。
ボーナスには様々な呼ばれ方がある
ボーナスは「賞与(しょうよ)」とも呼ばれ、同じ意味で使われることが一般的です。
また、企業や業界によっては「特別手当」や「期末手当」といった名称が用いられることもあります。
いずれも基本給とは別に支給される一時的な報酬であり、従業員の業績評価や会社の利益状況に応じて支給される点は共通しています。
こうした呼び方の違いはありますが、実質的には同じ制度を指していると理解して問題ありません。
必ず支給されるわけではない
ボーナスは必ず支給される保証があるわけではなく、法的に義務付けられてもいません。
企業の業績悪化や経営判断により、ボーナスの支給が見送られたり減額されたりするケースも珍しくありません。
たとえば、コロナ禍の影響で多くの企業がボーナスの支給を見合わせたり、大幅に減額した事例がありました。
そのため、ボーナスを含めた収入計画を立てる際は、こうした変動リスクを十分に考慮することが重要です。
2025年夏のボーナス動向|大手・中小・支給なし企業の実態を解説

2025年の夏季ボーナスは、企業規模や業種によって大きく差が生じています。
特に大手企業と中小企業の間で支給額に顕著な開きがあり、さらにボーナスを支給しない企業も一定数存在するのが現状です。
ここでは、それぞれの実態を具体的な数字をもとに詳しく見ていきます。
大手企業の平均支給額は97.4万円
2025年夏のボーナスにおける大手企業の平均支給額は約97.4万円です。
これは経団連が2025年8月8日に発表した調査結果によるもので、調査対象は原則として従業員500人以上の主要23業種、大手247社が含まれています。
2024年度と比較すると3.44%の伸びを示しており、景気回復や企業業績の改善が反映された結果といえます。
ただし、業績や個人評価によって支給額に差が生じる場合もあることは理解しておきましょう。
※参考:2025年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結結果(加重平均)【PDF】
中小企業を含めた平均支給額は45.7万円
一方、中小企業を含めた全体の平均支給額は約45.7万円にとどまっています。
これは2025年6月13日に発表された帝国データバンクの「2025年夏季賞与に関する企業の動向アンケート」の結果に基づく数値です。
同調査によると、企業の約3割で1人当たりの平均支給額が前年より増加しているものの、中小企業は資金繰りや経営環境の変動に影響を受けやすく、大手企業と比べてボーナスの支給額が低めに抑えられる傾向があります。
また、経済情勢の影響も大きく、企業ごとに支給額にばらつきが見られるのが特徴です。
※参考:2025年夏季賞与に関する企業の動向アンケート|株式会社 帝国データバンク
13%の企業がボーナスを支給しない現状
2025年の調査によると、約13%の企業がボーナスを一切支給していないことも明らかになっています。
このデータは先ほど紹介した帝国データバンクの「2025年夏季賞与に関する企業の動向アンケート」に基づくもので、業績悪化や経営判断が主な背景とされています。
特に景気の不安定な時期には、この割合が増加する傾向にあります。
こうした現状を踏まえ、ボーナスに過度に依存しない収入計画を立てることが重要です。
旅行業界のボーナス(賞与)事情|平均支給額と他産業との比較

旅行業界は景気や外部環境の影響を強く受けやすい業種であり、ボーナス支給額にもその傾向が表れています。
ここでは、Yahoo!仕事カタログの最新データをもとに旅行業界のボーナス支給額の実態と、他産業との比較、さらに支給額が低い背景について解説します。
Yahoo!仕事カタログによる平均支給額は26.3万円
Yahoo!仕事カタログに掲載されている大手旅行会社9社のボーナス支給額データをもとに独自に平均を算出した結果、旅行業界のボーナス平均支給額は26.2万円(半期)となりました。
なお、同データには口コミなどの情報も含まれているため必ずしも正確とは言えませんが、現実的な数値として業界の実態をおおむね反映していると考えられます。
今後の動向を把握するうえで参考になる数字です。
| 会社 | ボーナス(賞与)/半期 |
|---|---|
| 株式会社JTB | 41.0 万円 |
| 阪急交通社 | 32.5 万円 |
| エイチ・アイ・エス | 30.0 万円 |
| ジェイアール東海ツアーズ | 28.0 万円 |
| 東武トップツアーズ | 24.5 万円 |
| クラブツーリズム | 23.0 万円 |
| 日本旅行 | 22.0 万円 |
| 名鉄観光サービス | 18.0 万円 |
| 近畿日本ツーリスト | 17.5 万円 |
| 平均 | 26.3 万円 |
他産業と比べるとやや低い水準。その理由は?
旅行業界のボーナスが他産業に比べて低めにとどまっている背景には、業績の変動が非常に大きいことが挙げられます。
景気や国際情勢、天候などの外的要因により収益が左右されやすいため、安定した高額ボーナスの支給が難しい状況です。
加えて、人件費の抑制や激しい競争環境による利益率の低下も、ボーナス水準を押し下げる要因となっています。
さらに、新型コロナウイルスの影響で観光需要が大幅に減少したことも、業界全体の収益に大きな打撃を与え、ボーナスに反映されています。
こうした厳しい経営環境を背景に、業界では給与体系の見直しや福利厚生の充実を進めるなど、従業員の満足度向上に向けた取り組みが進行しています。
ボーナス(賞与)を増やす方法|収入アップの具体的なステップ

ボーナスを増やすためには、まず現在の働き方やキャリアプランを見直すことが重要です。
具体的には、昇格や昇進で月給を上げる方法や、ボーナス水準の高い業界への転職など、収入アップにつながる選択肢があります。
次章では、それぞれの方法について詳しく解説します。
昇格・昇進で月給を上げて支給額を増やす
昇格や昇進によって役職や責任が増すと、基本給が引き上げられます。
これによりボーナスの計算基礎となる月給が上がるため、結果的に支給されるボーナス額も増加します。
ただし、手当はボーナスの計算基準に含まれないことが多いため、給与の内訳を正しく理解することが重要です。
キャリアアップを目指す際は、業務に真摯に取り組むとともに、会社の評価基準や給与体系をしっかり把握し、自己成長を促すことが求められます。
ボーナスの高い業種や企業へ転職する
旅行業界に特化した情報発信サイトとしてはやや踏み込んだ内容かもしれませんが、ボーナス水準の高い業種へ転職することは、収入を増やす有効な選択肢の一つです。
金融業界やIT業界などでは、そもそもの給与やボーナスの基準が旅行業界より高く設定されているケースが多く、業界を変えることでボーナス額がアップする可能性があります。
ただし、転職先の企業文化や仕事内容との相性は非常に重要です。
転職を検討する際は、十分な情報収集と自己分析を行い、慎重に判断することが求められます。
おすすめの転職エージェント
まとめ
2025年のボーナス支給額は全体的に昨年より増加傾向にありますが、旅行業界のボーナスは他産業と比べてやや低い水準にとどまっています。
ボーナスの支給額は業界の業績に大きく左右されることを理解しておくことが重要です。
一方で、昇格や昇進による給与アップや、ボーナスの高い会社への転職など、収入を増やすための具体的な方法も存在します。
最新の業界動向を把握し、今後のキャリア形成や収入向上に役立てていただければ幸いです。